 漢字質問箱「もくじ」へ! ・・・ もくじ
漢字質問箱「もくじ」へ! ・・・ もくじ | 漢字質問箱LOG 過去の質問より |
|▼質問箱|漢字家族| |形声文字|Home Page| |
 漢字質問箱「もくじ」へ! ・・・ もくじ 漢字質問箱「もくじ」へ! ・・・ もくじ |
ぐるめぽっぽさん、投稿ありがとうございます。
この件につきましては、
『ばかげた筆順の強制』をご参照くださいね。(^_^)
補足資料として、『宣帝と儒者』も紹介させていただいております。
》「聞く」(きく)という字の耳の部分の
》一番下の横棒 (14画目?)は
》右側がはみ出ないのが正しいのでしょうか・・
■解字
会意兼形声。門は、とじて中を隠すもんを描いた象形文字。中がよくわからない意を含む。聞は「耳+音符門」で、よくわからないこと、へだたったことが、耳にはいること。
http://www.konton.net(ホームページ)
http://www.konton.net/kanji/(漢字家族)
http://www.konton.net/i/(i-mode用HP)
「聞く」(きく)という字の耳の部分の 一番下の横棒 (14画目?)は
右側がはみ出ないのが正しいのでしょうか・・
もちろん 新聞の文字、漢字辞典や 小学生の使う漢字一覧などは はみでてません。
いままで ずっと はみだして書いてました。(私の隣人もみんなそうです。)
で たまたま古い漢字字典をみたら はみでて書いてありました。
つまり 本当に 門に耳 の字になってたんですね。
これが 昭和22年監修 だったんですけど。
いったい いつから かわったんでしょう・・・。
そして 私に漢字を教えてくれた小学校の先生は どっちを教えたんでしょうね^^;
ついでに 「聖」の字も 耳は はみでないみたいです。
自分の解釈だけでは、ずいぶんと間違っていることが多かったです。ありがとうございました。
<愛>
■解字
会意兼形声。旡(カイ)・(キ)とは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
■単語家族
既(キ)(いっぱいである)・漑(カイ)(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀(アイ)(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
■音
アイ【漢音】 オ, アイ【呉音】
■訓
いとおしむ, いとしむ, めでる, おしむ
■意味
(1)いとおしむ(いとほしむ)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛すべし」
「愛厥妃=厥の妃を愛す」〔孟子・梁下〕
(2)めでる(めづ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」
「停車坐愛楓林晩=車を停めて坐に愛す楓林の晩」〔杜牧・山行〕
(3)おしむ(をしむ)。いとおしむ(いとほしむ)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」
「百姓皆以王為愛也=百姓皆王を以て愛めりと為す」〔孟子・梁上〕
(4)かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
<恋>
■解字
会意兼形声。戀の上部(音レン)は「絲+言(ことばでけじめをつける)」からなり、もつれた糸にけじめをつけようとしても容易に分けられないこと。乱(もつれる)と同系のことば。戀はそれを音符とし、心を加えた字で、心がさまざまに乱れて思いわび、思い切りがつかないこと。
■単語家族
乱・巒(ラン)(きりがなく連なって続く山々)・「戀-心+子」(ラン)・(レン)(もつれ連なってうまれる双生児)などと同系。
■音
レン【呉音・漢音】
■訓
こう, こい, こいしい
■意味
(1)こう(こふ)。こいしい(こひし)。断ち切れずに心が引かれる。思いわびる。いつまでも慕わしく心が乱れるさま。「留恋」「恋桟(レンサン)(職をほしがって執着する)」
「羈鳥恋旧林=羈鳥は旧林を恋ふ」〔陶潜・帰園田居〕
(2)こい(こひ)。男女が慕い合って思い乱れる気持ち。「悲恋」
つぎに、「愛」。
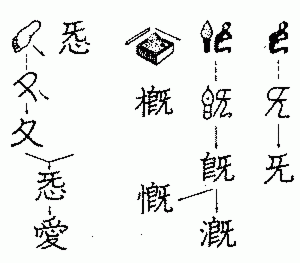
「胸いっぱいの切なさ」
== 引用はじめ ==
愛は「喜び」よりも「悲しみ」を与えるものだそうだ。およそ愛とは、異常な心の高まりだから、愛の心は必ず「切なさ」を伴うものだ。そして「切なさ」は、むしろ悲しみに近い。
愛という字は、昔は「旡+心+久」と書いた。今日の愛という字の下半部は原型のままだが、その上部は旡(カイ・アイ)のひどく変形したものである。この旡という部分は、アイという発音を示す大切な個所でもある。そこで、旡-既-慨-漑-概など、およそ旡を含むコトバを並べて考えてみる必要があろう。
旡とは、人間が腹をいっぱいにつまらせて、ウーンと後ろにのけぞった姿である。既の字は、お盆に盛ったごちそうを前にして、たら腹食べ終わった人間が、ウーンとのけぞっているさまを表す会意文字である。既の字の左側は付図のように、盆上に盛った丸いオマンジュウである。今日でも「いっぱい」になった状態を既(キ)という。たとえば日食や月食のとき、黒い蝕(ショク)の部分が、太陽や月の表面をいっぱいに食い尽くしたのを「皆既食」という。「し尽くした」のは「すでに終えて余白がない」ことだから、既には「すでに」という副詞の意味も生じてくる。
水をドクドク注いで田の面もいっぱいに満たすのを灌漑という。この漑(ガイ)とは、水を「いっぱい」にすることである。また、四角いマスでお米をすくい上げると、どうしても凹凸が生じてマスの隅々には米が行き渡らない。その時「マス掻き棒」を使ってサッと表面をならすと、お米はマスの隅々まで届いて、マスはいっぱいになる。「いっぱいに」ならす棒のことを概(ガイ)という。ならすという意味に傾くと、「大概」(ならす→おおよそ)とか「概略」(ならしたあらまし)という意味となるが、概の字の本義はマスを「いっぱいにする」棒のことである。最後に、心がいっぱいにつまるのを慨(ガイ)という。怒って胸がいっぱいになるのは憤慨、感動して胸いっぱいにつまるのは感慨という。そして、胸いっぱいの切なさ-それを愛というのである。それは心の姿だから、心の字をそえ、また切なさに足を引きずり、歩みも滞(とどこお)りがちとなるので、足ずりの形夂をそえた。それは憂(ユウ)の字の場合に、「心+夂」をそえたのと同じ意味である。
もっとも「切ない」のは恋しい場合だけとは限らない。「ああ、もったいない」という場合にも胸がいっぱいにつまる。だから愛情の愛は「おしむ」と訓じるのである。
斉国は偏小なりといえども、吾なんぞ一牛を愛(お)しまんや!<孟子>
ケチンボじじいが「ああ惜しい」と十円玉を哀惜する心と「あの子恋しや」と切ながる気持ちとを同一視されては、叱られるかもしれない。しかしどちらの愛も「胸いっぱいの切なさ」という点では同じなのである。
== 引用おわり ==

菊池さん。大変お待たせいたしました。
「愛」と「恋」について、まずは、絶版となった『言葉の系譜』(藤堂明保)から引用します。
それでは、「恋」から、
== 引用はじめ ==
ところで「もの思う」とは、どういう心理なのであろうか、いま戀(恋)の字の上部をみると、それは左右に糸を書き、中央に言の字を配してある。言とはズバリと裁断する明白なコトバである。糸が左と右にあって、容易に裁ち切れぬさまをにおわせたのが、この「戀-心」という部分である。してみると恋とは、まさしく糸が乱れて千々に乱れる、そのような心を表すコトバであろう。いったい今日の楷書は、秦の始皇帝が統一して定めた小篆の字体を継承したものだ。ところで、秦の統一のさい、採用されなかった古代文字、俗に「古文」と称する字体があるが、恋の字の古文は、ほとんど亂(乱)の字の左側と同じである。してみると、恋-乱は、きわめて近いコトバだということが判明する。
そこで亂とは何かを考えてみよう。その左側は、上と下とから手が差し出されており、その中間に糸巻きにもつれた糸が描かれている。つまり、糸がもつれて、ズルズルと結末がつかず、二本の手でさばきかねているさまである。右側の乙印は、後に加わったもので、軋(アツ)の右側と同じく、おさえて処理する意味をそえたものだ。乱 luanの語尾のnがtに転じると、luat(ラツ)という語形となり、寽・「寽+手」・埒などの字で表される。寽もまた、上と下とに手があり、中央に一印が描かれた会意文字だ。そこで寽や「寽+手」は、両方から物を取ろうとして引っぱり合い、容易にケリのつかぬさまを表している。日本語で「ラチがあかない」というそのラチは、この寽・「寽+手」を音訳した借用語なのである。乱-「寽+手」は同系の語で、もつれ合ってケリのつかぬこと、つまり「ラチのあかない」さまを意味する。
恋(レン)と近いのは、ケイレン(痙攣)の攣である。ケイレンとは、筋肉が上下から引っぱってもつれ合い、ラチのあかぬ状態である。二人以上の赤ちゃんが、もつれ合って生まれるのを攣生(レンセイ)という。これも恋(もつれ乱れた心)と同系である。そこで恋する者の心理は明らかとなった。恋(レン)とはつまり「乱(ラン)した心」、ちぢにもつれて収拾がつかず、ラチのあかない心理なのである。ああも思い、こうも思い、ケイレンしたようにズルズルとつながってケリがつかない、「あい見ての後」の、「もの思う」心とは、そうしたものらしい。
== 引用おわり ==
「愛」と「恋」の語源、成り立ちを教えてください!!
たっくんへ、お待たせしております。
これもとりあえず、解字から・・・(詳しくはのちほど・・・)
<扉>
■解字
会意兼形声。非は、両側にあいそむいて開いたさま。扉は「戸+音符非」で、左右に開くとびらのこと。
■単語家族
排(左右に押しあける)と同系。
■音
ヒ【呉音,漢音】
■訓
とびら
■意味
とびら。両側に開く二枚とびら。「柴扉(サイヒ)(そまつな木のとびら)」「丹扉(タンピ)(宮中の朱塗りのとびら)」
「方士抽簪扣扉=方士簪を抽きて扉を扣く」〔陳鴻・長恨歌伝〕
「扉」という漢字の語源は?
<磨>
■解字
会意兼形声。麻は「广(いえ)+麻の繊維をはぎとるさま」からなり、家の中で麻の繊維をはぎとるさまを示す。そのさい、こすりあわせて、繊維を細かくわける。磨は「石+音符麻(こする)」で、石をこすること。
■単語家族
靡(ビ)(こすって小さくする)・摩(こする)と同系。
■音
マ【呉音】, バ【漢音】
■訓
みがく
■意味
(1)みがく。玉や石をこすってみがく。
《同義語》⇒摩(こする)。
《類義語》⇒研(とぐ)。「研磨(ケンマ)」
「如琢如磨=琢するがごとく磨するがごとし」〔詩経・衛風・淇奥〕
(2)みがく。技術や学問をみがいて上達する。
「練磨(レンマ)」「切瑳琢磨(セッサタクマ)(学問や腕をみがきあう)」
(3)二つの円盤の形をした石に歯をつけてかさねあわせてもみ、回転させてその間に入れた穀物をすりつぶす道具。石うす。ひきうす。▽去声に読む。
《類義語》⇒磑(ガイ)(石うす)・碓(タイ)。
(4)すりへってなくなる。
※「摩」に書き換えることがある。「研摩・摩滅」
福本さん、超亀レスで申し訳ございません。
とりあえず、解字からまいります。
<摩>
■解字
会意兼形声。麻(マ)は、すりもんで繊維をとるあさ。摩は「手+音符麻」で、手ですりもむこと。
■単語家族
磨(マ)(石ですりみがく)・摸(モ)(なでる)などと同系。
■音
マ【呉音】, バ【漢音】
■訓
する, なでる, さする, みがく, せまる
■意味
(1)する。なでる(なづ)。さする。手ですりもんで、こする。「摩擦」「按摩(アンマ)(押さえたり、なでたりする)」
「剛柔相摩=剛柔相ひ摩す」〔易経・繋辞上〕
(2)する。みがく。こすってきれいにする。
《同義語》⇒磨。「研摩(ケンマ)(=研磨。といできれいにする)」
(3)せまる。触れ合う。また、そばに触れるほど接近する。
《類義語》⇒接。
「摩天楼」「剣槊相摩=剣槊相ひ摩す」〔蘇洵・送石昌言使北引〕
む「観摩(カンマ)」とは、なでつすかしつ、研究すること。
※「磨」の代用字としても使う。「研摩・摩滅」
マモウは摩耗、ケンマは研磨と覚えていました。しかし、広辞苑では「マモウは摩耗・磨耗」、「ケンマも研摩・研磨」、「マメツも摩滅・磨滅」と摩と磨のどちらでも同じですが、「マサツは摩擦」の摩のみ、「タクマは琢磨」で磨のみです。摩と磨の使い方と意味を教えてください。それと、よく使うケンマとマモウはどちらのマ(磨・摩)を使うのが一般的か教えて下さい。
粥
■解字
会意。原字は鬻で、粥はその略体。「弓二つ(かこう姿)+米+鬲(煮なべ)」。
容器にふたをして米を煮ることをあらわす。
■単語家族
蹈・陶・築・熟・毒・篤・融・忠(万遍なく行きわたる、平均する)
■音
[Ⅰ]シュク【呉音・漢音】
[Ⅱ]イク【呉音・漢音】
■訓
かゆ, ひさぐ, うる
■意味
[Ⅰ]かゆ。水をたくさん入れて、米をやわらかく煮た食べ物。おかゆ。《同義語》⇒鬻。
[Ⅱ]ひさぐ。うる。《同義語》⇒鬻。
「粥文=文を粥る」
「君子貧不粥祭器=君子は貧なれども祭器を粥らず」〔礼記・曲礼下〕
※州(シュウ)・・・全体に万遍なく行き渡らせる。
※酬(シュウ)・・・座にいる全員に洩れなく酒を行き渡らせること。
※周(シュウ)・・・周囲を取り囲むこと。字形は「田の中に万遍なく苗を植えた姿」
※調合・調整の「調」とは、ムラのないよう、全体に平均して行き渡らせる意味を含む。食物のうち、そうした状態を呈するのが「おかゆ」であり、それを表す漢字は、「粥」(シュク)である。周と同系。
また、「搗」や「蹈」とも同系であって、万遍なくトントンと叩いて、米粒をつぶし、柔らかくしたのが「粥」だと考えてもかまわない。
※「粥」の外側は弓ではなく、篆文の示すように、囲いをした姿である。「鬲」(レキ)は三脚の蒸し鍋で、中国の独特の炊事用の土器の形に象っている。
先日風邪をひいて、レトルトのお粥のお世話に」なりました。そこでふと思ったのですが、何で「粥」という字は左右に「弓」が付くのでしょうか?