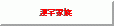 トップ
トップ 漢字家族
漢字家族┣ 渾沌(こんとん)
┣ 漢字家族について
┣ 漢字をむずかしくした人々
┣ コラム(補足説明)
┣ 文と字(漢字の種類)
┣ 象形指事会意形声
┣ 形声文字
┃┗ 大切に包む
┣ 転注・仮借
┣ 漢文の基本構造
┗ 漢字の話
 漢字質問箱
漢字質問箱
┣ 漢字質問箱
┣ 質問コーナー
┣ 筆順の強制について
┣ 宣帝と儒者
┣ 鶏肋(ケイロク)-鳥 隹 酉(とり)
┣ 鶏をさくになんぞ牛刀を用いんや
┣ 鶏口牛後(上の口、下の后)
┣ 鳥 隹 酉(とり)
┗ 「子・鼠」(ねずみ)
 リンク1
リンク1
┣ 渾沌のブックマーク
┣ 漢籍リンク集
┣ 藤堂明保博士著作
┣ 漢字能力検定協会
┣ 春秋戦国史(秀逸)
┗ 老人党公式サイト
 リンク2
リンク2
┣ 使えるツール
┣ グーグルツールバー
┣ 日本史&文学史辞書
┗ 渾沌のブックマーク
 渾沌のHP
渾沌のHP
┣ 渾沌のHP
┣ 作者:渾沌
┣ 司馬遼太郎記念館
┣ 教育催眠研究会
┗ e_mail
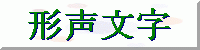
|
形声文字--はじめにことばありき |
|
形声文字 -- 旁(つくり)は意味を表す 形声文字については、一般的には次のような説明がなされています。
ある教科書(小学校用)では、次のように説明されています。
さあ、これをお読みになって、ご感想は? ここでいう「意味を表す部分」とは? 「音を表す部分」とは? 「音だけを表す部分」とは、いったいどういうことでしょうか? およそ、この世の中に、音だけを表して、意味を持たないことばというものがあるでしょうか? たとえば、あなたの隣にいる人が、突然「ホニャピー」と言ったとします。これは「ことば」といえるでしょうか?あなたにしてみれば、前後関係がわかっていますので、この人が「ホニャピー」と叫んだ意味がわかるかもしれません。ただし、その場にいなかった人に、何の脈略もなしに「ホニャピー」と言っても、意味不明でしょう。これが、音だけあって意味のない例です。ただし、これは「ことば」とはいえません。「意味のない音」は、けっして「ことば」とは呼べないのです。 「inu」という音が聞こえました。日本人ならすぐに「犬」を頭に描くことができます。これは、日本人の間では「inu」という音と、あの動物の「犬」を対応させる約束ができあがっているからです。つまりかんたんにいうと、日本人の間では、「inu」という音が「犬」という意味を持っているのです。 同じように漢字の本家中国でも、漢字が発明されるずーーーーっと以前から、ことばはあったのです。あたりまえの話ではありませんか。その時代には、「音」だけで意思疎通をはかっていたのであり、「音」だけで必要な連絡をし、自分の気持ちを伝えていたのです。でも、「音」はすぐに消えてしまいます。記録を残すには何かにとどめねばなりません。そこで漢字が発明されたのです。 漢字は、ことばの意味をできるだけうまく表すよう工夫されています。けれども、漢字がことばをまるごと表現できているわけではありません。そこで、私たちは、漢字を見るとき、漢字を発明した人の気持ちになって、そこで表現されようとしている「もとのことば」をさぐる必要があります。 たとえばここに、「家」という漢字があります。この字は「宀(やね)+豕(ぶた)」で成り立っています。それでは、「家」とは「ぶたごや」のことでしょうか?いいえ、違います。この漢字は「カ」ということばを表現するために工夫されたものです。この場合の「カ」とは、「したの物をカバーする、おおいをかける」という意味のことばです。われわれの住む「家」の最大の役目は、人や家畜をカバーして雨露から守ることです。だから、「イエ」のことを中国では、「カ−おおいをかけてカバーする」と呼びます。これは、「仮(カ)」や「庫(コ)」などと同系のことばです。 この字を発明した人は、「おおう、カバーする」という意味を表現するために、考えをめぐらせて、ついに「宀(やね)+豕(ぶた)」という組み合わせを思いつきました。それは、当時の家畜は羊や馬など、放牧(はなしがい)されることが普通だったのに対して、ブタは、その性質上、どうしても屋根の下で飼う必要があったのです。そこに着目して、カバーされる代表として「豕(ぶた)」を選んだのです。ただし、これは代表選手であって、屋根の下に人間がいるときでも、物が置かれていても、それを「家」という漢字で表現します。「カ--おおいをかけてカバーする」ということばを表現するために、たまたまブタをつれてきただけで、本当はなにをつれてきてもよかったのです。 また、ここに「婦」という漢字があります。この字は「女+帚(ほうきを持つさま)」で成り立っています。これを見て短絡的に「婦人とはお掃除女のことだ」と思うと、それは早合点です。さきの「家」の場合と同じように、倉頡(漢字の発明者)の気持ちになってみなければなりません。 この字は、「フ--ぴったりと寄り添う」ということばを表現したものです。つまり夫にぴたりとよりそう妻のことです。夫とペアをなす人のことだったのですね。この字は、付(つき添う)・服(ぴたりとひっつく)・副(主たる者にぴたりと寄り添う添え人)・備(添え人)などと同系です。みなぴたりとくっつく、よりそうという意味のことばを表現したものです。「婦」という字は、倉頡が婦人の動作の、ほんの一場面をスケッチしただけで、ことばをまるごと表現しているわけではありません。ここで、「ことば」を考えないで、字形だけを見ると「女+帚(ほうきを持つさま)、だからお掃除女のことだ」と誤解してしまうのです。字の形は、ことばのほんの一部しか表現できません。字形だけを見て勘違いをしないようにしましょう。 ここで、形声文字を例に挙げると、たとえば秘密の「秘」という字があります。これは、「示(かみ)+音符必」で、入り口をしめつけて内容がわからないようにした神秘なことを表します。この場合の「必(ヒ・ヒツ)」は、「ヒ・ヒツ--りょうがわからしめつける」という意味のことばを表す象形文字です。(棒切れを伸ばすため、両がわから、当て木をして、締めつけたさまを描いたもの)、秘密の「秘」は、泌(しめつけて汁をしぼり出す)・密(入り口をしめてかくす)などと同系です。この場合、おわかりのように、「ヒ・ヒツ」という音に意味があります。つまり、つくりの部分が「ヒ・ヒツ--入り口をしめつけて内容をかくす」ということばを表します。 してみると、「つくりは音をあらわす」ということは「つくりは意味をあらわす」ということなのです。だから、形声文字は、また会意兼形声文字と呼ばれます。言語学者は、漢字を「表語文字」と呼ぶことを提唱していますが、それは漢字が音と意味をあらわすもの、つまりことばを表現するものだからです。 けっして、「音だけをあらわし、意味はない」などという説明にまどわされないようにしましょう。 すると、「扁(へん)」の役割は何でしょうか。それは、その字の意味する物事の種別(その字が何に関係するか)ということを説明する補助的な役割なのです。こうしてみると、さきほどの形声文字の解説、
・・・は、明らかに誤っているといえるでしょう。 さきの説明のように、形声文字は一方は意味を、もう一方は音だけを表すということならば、音だけを表す必要性はどこにあるのでしょうか? 文字は、意味を伝えてくれなければ、それこそ意味がないのです。 どうして、こんなヘンな解説が、まことしやかに行われているのでしょうか?それは、日本に、漢字が文字として輸入されたからです。もちろん、最初に漢字を持ち帰った人は現地の音で読みこなせたのですが、訓読が発達するにつれて、漢字がことばを表現したものであることを忘れてしまったのです。だから、こんなヘンテコリンな説明がなされるのです。・・・ <つづく> ■漢字家族--漢字の語源・ワードファミリー解説
|