 「安んずる所なり。宀の下、─の上に従う。会意。指事。多の省声」 ・・・多は意符であり音符ではない。
「安んずる所なり。宀の下、─の上に従う。会意。指事。多の省声」 ・・・多は意符であり音符ではない。肉を整然とかさねて、宀(やね)の下においたさま。
神への供物が、形よく整うことを示す会意文字。
<倉頡篇> の「宜とはその所を得るなり」という解釈は、<説文> のものよりも明快である。かどあるさまを意味する点では、義・儀 と同系である。なお、
<礼記、王制> 「社に宜す」。
<爾雅、釈天> 「大事をおこし、大衆を動かすには、必ずまず社に事(つか)うるあり、しかる後、出ず。これを宜という」。
の二条は、宜(供物を整えて祀る)の原義をよく保存した用例である。
※ 『漢字語源辞典』(学燈社) p.592
字
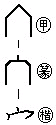 会意。
会意。「宀(やね)+多(肉を盛ったさま)」 で、肉をたくさん盛って、形よくお供えするさまを示す。
転じて、形がよい、適切であるなどの意となる。
(注1) 【宀】 (メン[呉]、ベン[漢] 屋根、おおい)
(注2) 【多】 (夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す)
味
「宜其室家=其の室家に宜しからん」〔詩経・周南・桃夭〕
(2) むべ。当然である。「不亦宜乎=亦た宜ならずや」
「宜乎=宜なる乎」〔孟子・梁上〕
(3) よろしく…べし。したほうがよい。するのがよかろう。
「宜鑒于殷=よろしく殷に鑒みるべし」〔詩経・大雅・文王〕
(4) (ギす)出陣を告げるために、社(土地の氏神)をまつる。また、その祭り。
「宜乎社=社に宜す」〔礼記・王制〕
族
 我-義-宜-雁-岸-顔-言 ・・・ かどばっている の 家族
我-義-宜-雁-岸-顔-言 ・・・ かどばっている の 家族